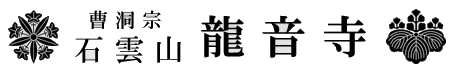お寺の歴史
石雲山龍音寺は、明徳元年(1390)、覚翁とい う旅の僧が当地を通りかかり、山の麓に白い苔 の生えた巨大な霊石を見つけ、ここに庵を開き、 石雲庵と名ずけたのが始まりと伝えられており ます。後に、伊豆河津の浜辺に流れついた観世 音菩薩尊(等身大檜一本彫・平安時代作)をお 迎えしました。 無住の時代もありましたが、永正7 年(1510) に、曹洞宗の僧侶である越渓麟易(真興正続禅師、?- 1514)が、石雲山龍音寺として 再建され、曹洞宗のお寺として栄えてきた歴史のある由緒正しきお寺です。

- 本堂
山門
寺院の入り口のことで、三門とも書きます。 古くは「玄関」とも呼ばれていましたが、そ の名残として、今でも皆様のご自宅の入り口 のことを「玄関」と呼んでいます。曹洞宗改 宗500 年記念として再建いたしました。龍音寺 の山門は、珍しい唐門風の造りになります。

- 山門
石雲
石雲と名付けられ、白い苔の生えた霊石は現 在も境内にあり、本当に白い雲の様に、白い 苔がびっしりと生えています。幾たびにも及 ぶ土砂崩れによって、その大部分は地中の中 ではありますが(それでもかなりの大きさで す)、白い苔の生えた霊石は石雲と名付ける に相応しく、雄大に境内にたたずんでおりま す。この巨石は、何千年もこの地を護持して きたました。因んで山号を石雲山と言います。

- 石雲
夫婦槙
樹齢六百年の槇の木で、山門入ってすぐに目の前に見えます。 根の部分は繋がっていて、互いを支えあっているようであり、 季節になるとたくさんの実を結ぶことから、「夫婦槙」と呼ばれ ています。
お寺がこの地に開かれた頃から存在し、この地を 守ってきました。晴れた日には木の間からも富士山を見ること が出来ます。

- 夫婦槙
慈母観音さま
山門を入ってすぐ左にたたずんでおります。
慈母観音さま は、お母さんが我が子に対するがごとく、どこまでも深く 大きい慈愛の心を表わした観音さまです。
手前にある手洗 い鉢でお水を頂いて、「わらべ」にお水をたむけてお参り 頂きます。

- 慈母観音さま
やすらぎ地蔵さま
山門を入ってすぐ右にたたずんでいおります。 お寺の中で、「ほっ」と、やすらげるように、2010 年に安座し、開眼いたしました。
お寺にお参 りした際には、手を合わせて、お参り下さい。 お地蔵さんが、手を合わせてにっこりと微笑 みかえしてくれます。あるいは、小さなお子 さんと一緒に頭をなでて、お勉強ができるよ うにお願いしてみてください。

- やすらぎ地蔵さま
ほほえみ六地蔵さま
山門を入ってすぐ右、「やすらぎ地蔵さま」のとなりのにたたずんでおります。
自然と笑顔になってほほえんで頂けるように、2014 年に安座し開眼いたしました。
お寺にお参りした際には、手を合わせてお参り下さい。
六体のお地蔵さまが、それぞれかわいらしく「ほほえみ」かえしてくださいます。
お地蔵さまは、弱い人から優先して守る仏さまとして知られ、古来より子供や地域の守り仏としてお参りされてきました。どうぞ、みなさまでお参りいただきたくおもいます。
きっと、お地蔵さまが、やすらぎとほほえみを与えてくださいます。

- ほほえみ六地蔵さま
聖観音さま(永代供養塔)
永代供養塔に鎮座しております。お寺の境内 を一望するように、そしてお顔は霊峰富士を まっすぐに見つめ、龍音寺を護持しておりま す。観自在の名がしめすように、普く方向に 慈愛の目を向けております。

- 聖観音さま(永代供養塔)
この他、本堂には、龍音寺観音菩薩(市指定文化財)、龍音寺観音菩薩切画二軸がまつ られおり、客殿内には石雲山龍音寺というお寺の名前からイメージされた、九尺×十尺の 大きな岩上観音画がまつられております。